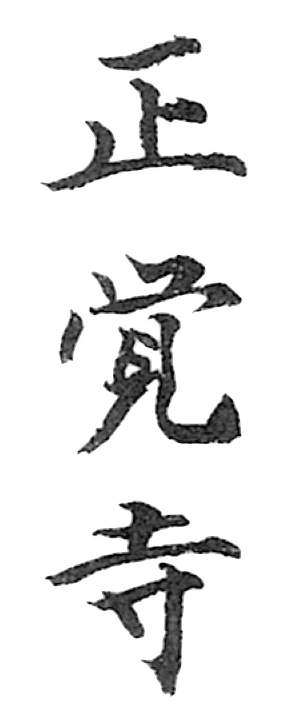今九州国立博物館で、「法然と極楽浄土」という展覧会があってます。これは親鸞聖人のお師匠である法然聖人が、お念仏のお救い、浄土宗が開かれて八五〇年になる記念のイベントだそうです。東京、京都とまわり、最後が九州となりました。
そのチラシを見てますと、どうしても観たいものがありました。
奈良の當麻寺に伝わってきた當麻曼荼羅です。奈良時代に作られたとされる、葛折の掛け軸です。非常に大きく縦横とも四メートルあります。奈良時代のものですから、かなり傷みが激しく、當麻寺に行っても観ることができない国宝です。十一月十一日から十一月三十日までの限定公開だそうです。
その題材は浄土真宗の根本聖典の一つ、観無量寿経(観経) の内容を絵で表したもので、観経に文章で説かれているお浄土の様子が絵になっていて、お浄土がイメージしやすくなってます。ある方に教えていただいたのですが、親鸞聖人が亡くなった後すぐの初期真宗寺院には、この當麻曼荼羅の縮小版があり、絵を指し示しながら阿弥陀仏のお救いの話をしていたそうです。絵を使いながら教えを解く事を「絵解き」と言います。今回のご縁であります報恩講では、いつも本堂の余間に親鸞聖人の御絵伝をかけますが、その頃はこの御絵伝も絵解きをして、親鸞聖人と阿弥陀仏のお救いの話をしていたとのことです。
観経以外の根本聖典「無量寿経」「阿弥陀経」でもお浄土の様子は非常に事細かく説かれています。真宗の偉い先生方から、ご法話の中であまり浄土の様子を話すべきではないと言われておりましたが、私は改めてこのお浄土の様子がお経に詳しく出てくる意味を大事にしたいと思うのです。
人間は、他の哺乳類に比べて視覚が優れています。「百聞は一見にしかず」といわれるように、見ることを大事にしているといえます。見ることが出来るもの、イメージが出来るものは理解しやすく感じます。逆にイメージしにくいものは難しく感じるものです。
阿弥陀仏を阿弥陀如来ということもあります。「仏」も「如来」も覚りを開いた方の尊 称です。この如来というのは、「如」より「来」たものという意味です。如とは真如、「空」 ということを表しています。しかし、空と言われてもどう受け止めて良いかわかりません。親鸞聖人は空のこと「色もなし、形もましまざず、言葉も絶えたり・・」と表現されてい ます。つまり、私たちのイメージできる限界を超えているので、私たちには捉えることが できないのだ、とあきらかにしてくださっているのです。
そのとらえるのことの出来ない「空」である仏様が、自ら私たち人間に分かるように形をとり色を示し、イメージ出来るようにお浄土をしつらえて下さっているのです。
まさに阿弥陀様は、真如から私たちの方へ来て下っている仏様なのです。思い浮かべることができるお浄土を通して、阿弥陀様は私たちに伝えたいことがあるのです。
この度の御法話は、私住職がさせていただきますが、このお話をさせていただきたいと 思います。どうぞお誘い合わせの上、お参り下さいますよう、よろしくお願いいたします。
また、二十七日には、余間にかけている御絵伝の前で絵解きの真似事をさせていただきます。楽しみにされてください。
『正覚寺報 第291号 2025年 報恩講』掲載