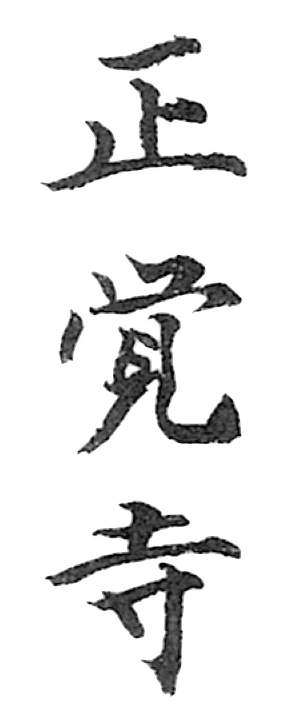先日、ある事件がタイの仏教会を揺るがしているというニュースを見ました。
高僧たちが僧侶にあるまじき行為をしたというスキャンダルをネタにゆすられ、ある女性に何億というお金を払っていたというのです。
タイの仏教は、スリランカと同じく部派仏教と呼ばれ、古い形の仏教で非常に厳格な戒律を守ることを特徴としています。戒律の中には車輪のあるものに乗ってはならないというものもあり、いまだに列車にも自動車にも乗らないという僧侶もいるそうです。そのように戒律を守っているから尊敬を集めていた僧侶が、戒律を蔑ろにしていたということで大変な事態になっているというのです。
戒律を一生守って破らずに生きていくことを誓ったお名前を「戒名」と言います。戒名は本当は亡くなってつけてもらうものではありません。仏教ではそれほど重要視される戒律ですが、戒律を守ることにどんな意味があるのでしょうか?
「戒律」と言いましたが、実は「戒」と「律」で意味が違います。「戒」は仏教の教えを 基準に自分で決めた戒め、自分が守るべきと決めたポリシーというとわかりやすいかと思います。「律」はほかの僧侶や周りの人との関係で仏教の教えに従って決めたルールです。どちらもその中心に仏教の教え、考え方があるのです。
部派仏教では、半月に一度お釈迦さまの時代から続く「布薩」という行事があるそうです。そこでは、その寺院に集う僧侶が全員出席し、一つ一つの戒律を挙げ、その戒律を破ったものは自ら告白するそうです。戒を守らなかったことは、一生戒を守る誓いをした僧侶にとっては重大な問題ですが、そこで自ら告白することでその戒を破ってはいないという扱いになるそうです。
なにか甘い処置のように感じますが、ここに仏教の特徴が表れていると思います。守っているかいないかではなく、戒律を守る生活をすることを通して、仏教ではなぜそんな行動をするのかを考え、仏教という教えを受け止めようとしていきます。戒律を破るという失敗を通しても、仏教の意味を学んでいくことが大事なことなのです。
「スーダラ節」を歌うことになった植木等さんは、とても悩まれたという話しを聞きました。映画の役と違い非常にまじめであった植木さんは、一番有名な歌詞の部分「分かっちゃいるけど止められない」がどうしても許せず、浄土真宗の僧侶であった父親にその思いを話したそうです。自分の意見に同意してくれると期待していたそうですが、帰ってきた答えが「『わかっちゃいるけどやめられない』は人間の矛盾をついた真理で、親鸞の教えに通じる」などと励まされたそうです。
親鸞聖人は、この世界の無常さ、自分という人間性の問題によって、どのような簡単な戒律も守れない時があることを嘆かれております。そのような人間を救う為に、阿弥陀仏の救いがあるのです。
阿弥陀様は、すべての人を必ず救うと誓われ仏となられた方です。その「すべて」を一人の人間の話と受け止めなおしますと、どんな人格であってもどんな人生であっても必ず救うという事になります。「分かっちゃいるけど止められ」ず仏教の教えをないがしろにしてしまう私でも、阿弥陀様は決して見放しません。失敗をしながらでいいから仏教を大事に生きておくれ、という阿弥陀様の思いが表れていると思うのです。
私達は守ると決めたことが守れなかった時、守ると決めた時の決意を忘れ、価値がなかったとあきらめ、もう一度守ろうとすることを止めてしまいがちです。そんな心の弱さをご存知の阿弥陀様のお救いが、私の心を支えもう一度、何度でもチャレンジをして行けるようにしてくださるのです。
現代社会は、なぜか失敗が許されないことになっています。そのような世界だからこそ、余計に阿弥陀様のお救いの支えは有り難く感じます。どうぞお寺にお参りいただき、仏教の教えをお聞きくださいませ。
『正覚寺報 第290号 2025年 秋彼岸法座』掲載